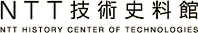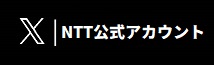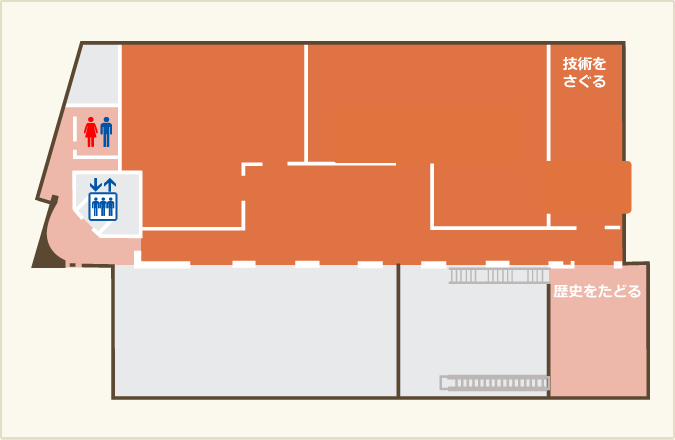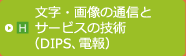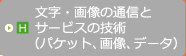展示パネル情報
3階フロア
文字・画像の通信とサービスの技術
ネットワークで使うコンピュータ(DIPS)、昔の電報・コンピュータ時代の電報(電報)
ネットワークで使うコンピュータ
日本のコンピュータ産業の基礎を築いた大型汎用機〈DIPS〉シリーズの開発

電電公社ではデータ通信システムの急速な普及に対応するため、ネットワークで使う大型コンピュータの早期実現をめざして1968(昭和43)年に国産汎用機メーカ(日本電気、日立製作所、富士通)と共同研究体制をとってDIPS開発計画を開始した。DIPS開発計画では、標準化、オンライン用電算機システムの実用化、電子交換、新伝送方式との親和性、信頼性の向上、経済化をねらいとした。1991年まで、自主技術開発、各種標準化、性能向上を数次にわたって行い、わが国のオンラインコンピュータ技術、大規模ソフトウェアの工業的開発技術の発展に多大な貢献をした。また、日本のコンピュータ産業の指導者を輩出するなど多数の情報処理技術者を育成するとともにその後のマルチベンダ展開への基礎を築いた。
大規模・高性能・高信頼をめざして
本体系と方式構成技術の歩み

DIPS-1では世界に先駆けて、オンライン用としてマルチプロセッサ、ローカルメモリ、仮想記憶の3方式を統合。DIPS-11では技術先導性を発揮し、通信制御処理などの専用プロセッサ化による分散処理方式、光ループによる複合構成方式などの技術開発を行い、大規模・高性能・高信頼なコンピュータを実現した。
※本体系とはコンピュータシステムを構成する装置群のうち、論理装置、主記憶装置、転送制御装置のデータ処理を行う装置の総称である。

DIPS-1の開発と成果

DIPS-1システム全景(1972年)

DIPS-11/45の開発

DIPS-11本体系の技術
柔軟性・機能分担の拡大・制御の共通化
通信制御技術の歩み

DIPSの通信制御では、わが国で初めて独立の専用プロセッサを用いた7300CCP、適用領域の拡大のために汎用マイコンを用いた7400CCP、世界に先駆けデータフロー概念を採用したICAなど、機能、性能、価格性能比に優れた特長をもつハードウェアを開発した。
- 多種類の回線・プロトコルを効率的に混在制御、および回線の増設・変更に柔軟に対応。
- ホスト負荷を軽減するため、高位レイヤまで処理を分担。
- 小型機から中大型機まで通信制御機能を共通化。
※通信制御処理装置はホストコンピュータと通信網の中間に介在し、端末と送受信する電文に対し、プロトコルに基づく処理を行う。
複数の機器を集中的に監視制御
システム制御技術の歩み

DIPS-1では、システムを構成するセンタ内の装置の電源制御、切替え制御などのハードウェア制御を集中して行う集中監視制御方式(CSC)を開発した。11/5Eシリーズでは、複合構成システムの実現に合せ、1本のループ状の制御ケーブルにより各装置を接続し、センタ内の全装置のハードウェア制御を集中して行うシステム制御プロセッサ方式(SCP)を開発した。これにより、運転監視操作の集中化、自動化、およびプロセッサの追加などのシステム構成変更に柔軟な対応を可能にした

複合構成システムへの発展
素子の集積度の向上を背景に
小型プロセッサ開発の歩み

社内システムを中心とした小型プロセッサの需要顕在化と論理素子の集積度の向上を背景に1979年にDIPS-VLSI開発計画を開始した。1984年に最初のモデルV20を開発。その後、半導体技術の進歩を取り入れ、高性能化、小型・経済化、および各種機能の拡充を進め、適用領域の拡大を図った。

DIPS-V20プロセッサの開発

DIPS-V40EX
大容量記憶装置とデータベース
ファイル系技術の歩み

データ通信システムの急速な発展を背景に、ファイル記憶装置の大容量化、高速化をねらいとした技術開発を進めた。1968年に大容量浮動ヘッド磁気ドラム記憶装置を開発、また小型高密度の大容量磁気ディスク装置、集合形大容量記憶装置、光ディスク記憶装置、リレーショナルデータベース専用マシン(RINDA)などを開発した。
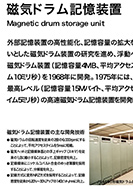
磁気ドラム記憶装置

大容量・高速磁気ディスク装置

大容量光記憶装置

リレーショナルデータベース専用マシン(RINDA)
制御プログラムを軸に多様なシステム展開
ソフトウエア技術の歩み

中大型・小型システム、通信制御プロセッサなどを含むネットワーク全体を統一的に制御するOS、複合構成システム対応OSなどの制御プログラムを核に多様なシステムの実現に貢献した。

ソフトウェアの階層アーキテクチャ

複合構成システムの主要技術

大規模データベース方式

ソフトウェア生産技術
スムーズな異機種間通信のために
ネットワークアーキテクチャ技術の歩み

コンピュータのネットワーク化の進展に伴い異機種のコンピュータ間での通信の必要性が高まり、NTT研究所ではネットワークの標準化を推進するために、1977年に製造会社4社とDCNAの共同研究を開始した。1978年にDCNA第1版を完成、引き続き開発を行い、1983年の第5版で共同研究を終了した。DCNAの研究成果は国際標準ネットワークプロトコルOSIに反映された。
(DCNAのねらい)
- 階層化した通信モデルによる異機種コンピュータ間通信の実現
- X.25プロトコルにもとづくディジタルパケット交換網の有効利用
- 高位プロトコル設定による分散処理の実現

ネットワークノードの階層構成
世界共通のインターフェースに向けて
マルチベンダ対応への歩み

マルチベンダ、マルチプラットフォームのコンピュータシステム同士でインタオぺラビリティ、およびプログラムポータビリティを確保するには、それらの各種コンピュータインタフェースの統一が不可欠である。NTTは内外ベンダ5社と共同研究を進め、汎用計算機の調達仕様としてMIA第1版を1991年に開発した。一方、欧米のキャリアでも同様の国際標準化活動(SPIRIT)があり、NTTはこれに参加し、MIAの成果を提案するなど多大な貢献をした。

MIAの概要

SPIRITの概要
昔の電報・コンピュータ時代の電報(電報)
昔の電報・コンピュータ時代の電報(電報)
電気を使って文字を送る糸口をつかんだのは19世紀初め。その後、幾多の努力によってモールス電信を生んで自動化を完成する一方、印刷電信による電信交換という新たな分野を開拓した。そして近年は、コンピュータ技術の導入を進め、マルチメディア技術を駆使した多様なサービスを展開するまでに至っている。
実務の情報から心情の情報へ
電報の役割の変化を送達紙から読む

緊急時の連絡手段として利用されていた一般電報は、電話の普及とともに取扱数は減少したが、人生の節目である慶弔の際の〈言葉のギフト〉として、慶弔電報の取扱数が増加した。1985年からは、メロディやおし花を添えて言葉を贈るさまざまな付加価値電報も登場している。

電報送達紙の系譜
創業期は手書き送達紙が用いられ、毛筆による手書きだったが、複写用炭酸紙が普及するとペン字になり、和文タイプの出現でタイプ字となった。その後、印刷電信機の導入とともにプリンタの印字テープを貼付した送達紙を使用するようになった。さらに現在では、レーザープリンタから直接印字し、送達紙を出力するようになっている。1985年にメロディ電報を発売し、その後さまざまな付加価値のある送達紙で電報サービスを行うようになった。
電報中継機械化方式の開発
人手による中継から自動中継機械化方式へ
近代的電報中継網の形成
人手による電報中継処理には、誤りと所要時間の増大といった課題があるため、その解消に向けてわが国をはじめ諸外国でも機械化が真剣に検討された。わが国では、1953年、紙テープを利用して電文を蓄積交換するTX形電報中継機械化方式を水戸局に導入し、世界に先駆けて自動化を実現した。その後、1955年にわが国標準の中継交換機TX-4形、1962年に東京中央電報局(大総括局)へTX-5形、1965年に大阪中央電報局へそれぞれ導入し、1966年の下関電報局へのTX-4形導入により、全国中継の機械化が完了した。

印刷電信から全自動電報中継網へ
19世紀の中頃からモールス電信機が普及する一方で初期の印刷電信機も誕生し、わが国でも輸入機による印刷電信が1927年から始まり、モールス通信に代わって電報の主流となった。その後、電報通数の増加につれ中継要員と伝達時間が増える対策として、1953年、世界に先駆けて中継機械化方式を開発し、1966年には全自動電報中継網の全国導入を完了した。なお、トラヒックの少ない取扱所では模写電送機が効力を発揮した。

TX-1形電報中継交換方式
発信加入局で付けられた宛局符号が、自動的に交換局装置を作動させ、着信加入局に電報を中継する方式である。交換局には収容加入局ごとの入・出中継席があり、交換機が入中継席で受信した宛局符号によって出中継席を選び、これら中継席の紙テープ送・受信機を介して電文を蓄積交換する。

電報中継機械化時代の電報業務の流れ
機械化前の電報は、発信から着信までに平均して1.8回の人手による中継を要していたが、全自動テープ中継交換方式により完全に自動化された。発信局取扱者の入力する宛局符号を電報中継交換装置で読み取り、自動で着信局へ接続し電文を伝送する。経費の削減のみならず、誤字の減少や伝達時間の短縮などサービスの改善を図ることができた。

放電記録方式が生んだ模写電報
心線使用効率と柔軟性の確保を両立
電報とコンピュータ
作業の省力化と漢字かな混じり文の登場
メッセージ交換方式が変えた電報の世界
電報システムのコンピュータ化
1950年代から電報中継機械化を始めたが、1980年代に入って一層のサービス向上と省力化をめざし、コンピューター化を進めてきた。1986年に電報そ通のための電報そ通システム(TXAS)、1988年には海岸局における船舶との電報そ通のための海岸局無線電報システム(SMART)を導入した。
TXASが実現した新しいサービス
本格的な漢字交じり電報を取り扱うなどの新規サービスを実現するとともに、手作業であった宛局先指定や料金計算の業務を自動処理化した 。

電報の申込みから送達まで
新しい電報そ通システムの登場
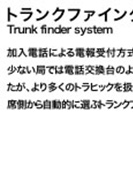
1993年に、新規サービスへの対応と保守運用性向上のためにTXAS-IIが登場した。サービス面では、文例のみに限られた漢字使用を自由に利用できるようにし、電報入力装置や電報出力装置の処理能力強化と、センタホストのホットスタンバイ化など多くの改善を施した 。
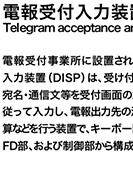
電報受付入力装置
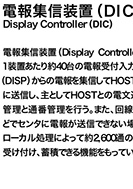
電報集信装置(DIC)
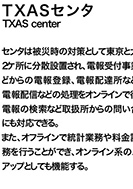
TXASセンタ
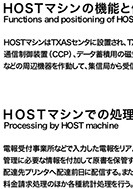
HOSTマシンの機能と位置付け
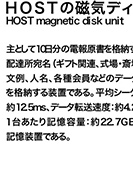
HOSTの磁気ディスク装置

高機能形電報出力装置(NPR)
マルチメディア技術で多様化する電報サービス

TXASは幾多の改善が施され、1999年からはDREAMSとしてサービスを提供している。パソコン通信、インターネット、FAXによる受け付けや、静止画像を含む電文編集など、マルチメディア技術を駆使した多様なサービスを実現している。また、オープンなプラットフォームやソフトを利用してシステムの経済化を図っている。